 |
NO.70 2006・01.20 | |

 |
NO.70 2006・01.20 | |

| 病気は上・頭・肩から、鼻・口・皮膚から入ります。この病気になった始めを“表(ヒョウ)”とします。もう少し病気が体内に入って続くと“裏(リ)”と言います。発熱があって暑がり顔が赤かったら“熱(ネツ)”、熱があっても寒がり顔が青白いと“寒(カン)”。体格がよく体力があれば“実(ジツ)”、やせていかにもひ弱なら“虚(キョ)”と判定します。表・熱・実をあわせて“陽”、裏・寒・虚を“陰”と言います。この陰陽・表裏・寒熱・虚実を“証(ショウ)”と言い、この“証”が西洋医学の病名にほぼ匹敵します。 病気になった人(患者)・病期を、顔色や身体つきや舌を見て(望)、話声や呼吸音を聞き(聞)、何時からどんな症状があったか質問して(問)、脈やお腹を触って(切)診察します。身体は気血水(キケツスイ)の順調な発生と流れで健康が保たれ、気の異常な発生や血水の停滞で病気になり、これを直すことが治療とされます。 |
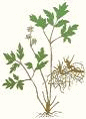 いくつかの生薬を組み合わせて薬を作ります。生薬は薬草と言われる植物が多いのですが、動物や鉱物もあります。植物は根・茎・樹皮・果実・種などを使います。薬草と言えば特別な植物のようですが、稲(粳米コウベイ)、ゴマ(胡麻)、小麦(ショウバク)、ショウガ(生姜ショウキョウ)、ゴボウ(牛蒡子ゴボウシ)、シソ(蘇葉ソヨウ)、ミカンの皮(陳皮)、ウド(独活)など日常の食べ物もあります。桃の種(桃仁トウニン)、ビワの葉(枇把葉ビワヨウ)、アケビの茎(木通モクツウ)のように食べない部分を使うものもあります。変わった物ではセミの抜け殻(蝉退ゼンタイ)、石膏(セッコウ)、滑石(カッセキ)、カキの貝殻(牡蠣ボレイ)、化石の骨(竜骨リュウコツ)などもあります。 いくつかの生薬を組み合わせて薬を作ります。生薬は薬草と言われる植物が多いのですが、動物や鉱物もあります。植物は根・茎・樹皮・果実・種などを使います。薬草と言えば特別な植物のようですが、稲(粳米コウベイ)、ゴマ(胡麻)、小麦(ショウバク)、ショウガ(生姜ショウキョウ)、ゴボウ(牛蒡子ゴボウシ)、シソ(蘇葉ソヨウ)、ミカンの皮(陳皮)、ウド(独活)など日常の食べ物もあります。桃の種(桃仁トウニン)、ビワの葉(枇把葉ビワヨウ)、アケビの茎(木通モクツウ)のように食べない部分を使うものもあります。変わった物ではセミの抜け殻(蝉退ゼンタイ)、石膏(セッコウ)、滑石(カッセキ)、カキの貝殻(牡蠣ボレイ)、化石の骨(竜骨リュウコツ)などもあります。たくさんの生薬をいくつか組み合わせてひとつの処方薬を作ります。一定の組み合わせに名前がついていて、これが葛根湯とか小柴胡湯とかと言う薬の名前になります。 |
 原則のやり方は各生薬を測って処方薬を作ります。昔の医者は同じ処方名でも患者の状態で各生薬の量を少し増やしたり減らしたりしていました。これから“さじ加減”と言う言葉ができたわけです。今でも純粋の漢方医や中国で研修してきた医者はこの方法で薬を調剤します。患者はこの調剤された生薬を家で、お茶を作るように煎じて飲むわけです。このやり方は手間がかかるので、煎じた液を粉末にする技術ができ、普通の粉薬のようにした製品ができました。これを“エキス剤”と言います。エキス剤ができ、保険でも漢方薬が処方できるようになって、一般の病院でも気軽に使用されるようになりました。今ではエキス剤を固めて錠剤にしたり、カプセルに入れた漢方薬もあり、西洋薬と同じ飲み方ができます。ただ、“生薬がひとつでも加わると別の薬になる”という漢方薬の原則から言えば、粉末を固めるものやカプセルが加わることになるので“邪道”との見方もあります。また、“煎じて飲む”薬なのでエキス剤でもお湯で飲むべきとも言われます。 原則のやり方は各生薬を測って処方薬を作ります。昔の医者は同じ処方名でも患者の状態で各生薬の量を少し増やしたり減らしたりしていました。これから“さじ加減”と言う言葉ができたわけです。今でも純粋の漢方医や中国で研修してきた医者はこの方法で薬を調剤します。患者はこの調剤された生薬を家で、お茶を作るように煎じて飲むわけです。このやり方は手間がかかるので、煎じた液を粉末にする技術ができ、普通の粉薬のようにした製品ができました。これを“エキス剤”と言います。エキス剤ができ、保険でも漢方薬が処方できるようになって、一般の病院でも気軽に使用されるようになりました。今ではエキス剤を固めて錠剤にしたり、カプセルに入れた漢方薬もあり、西洋薬と同じ飲み方ができます。ただ、“生薬がひとつでも加わると別の薬になる”という漢方薬の原則から言えば、粉末を固めるものやカプセルが加わることになるので“邪道”との見方もあります。また、“煎じて飲む”薬なのでエキス剤でもお湯で飲むべきとも言われます。 |
| 西洋薬にはない漢方の使い方に“未病を治す”というのがあります。“未病(ミビョウ)”とは“今はまだ病気になってはいないがこのままだと病気になる”状態です。西洋医学では病気・異常には薬がありますが、予防は予防接種だけで、あとは食事や生活の養生です。漢方薬には免疫を上げたり、アレルギーを抑えたり、身体のフォメオスターシス(恒常性)を保つ作用があります。体調が悪い・元気がない・なんか変・朝起きづらい・食欲がないなどの症状があっても診察・検査で異常・病気がなければ西洋薬は処方できませんが、漢方薬ではいくらでも薬があります。ですから最近、更年期障害・自律神経失調症などに漢方薬を出す医者が増えてきました。 |
![]()
![]()
![]() 田村こどもクリニック~クリニックだより
田村こどもクリニック~クリニックだより ![]()
![]()
*田村こどもクリニック*
http://www.inforyoma.or.jp/tamkocli/