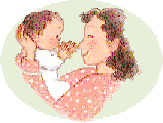 |
こうちぼにゅうのかい 高知母乳の会 |
第17号 発行日 2008.6.10
|
||||||||||||
| 発 行:高知母乳の会 会 長:福永寿則 事務局:田村こどもクリニック |
〒783-0006 高知県南国市篠原1459-1 TEL088-863-0723 |
|||||||||||||
● 第27回定例会報告 : 四国交流会 ● テーマ 平成20年5月11日、国立高知病院地域研修センターにて第12回高知母乳の会総会・第27回定例会が開催されました。今回の定例会のテーマは「四国交流会」。参加者は24名、県外からも様々な立場の方が参加されていました。小グループに分かれての話し合いは時間が足りないほど白熱し、有意義は交流となりました。定例会では、まず国立高知病院の高橋医師より、高知県の新生児医療の現状や国立高知病院の新生児医療や母乳育児支援の現状のお話があり、四国交流会にあたってのいくつかのテーマ提供をして下さいました。 その後、4〜5人の小グループに分かれて自由テーマでの話し合いが始まりました。自己紹介の後、各グループ活発は話し合いとなしました。 全体では、香川県の病院での母乳育児支援の取り組みも紹介されました。各グループからの話し合いの内容や感想を全体で共有する時間が十分に取れないほど活発な話し合いとなりましたので、各グループから把握できた分の話し合いの内容に関しては以下の通り箇条書きで掲載させていただきました。 ≪私たちはこんな話をしました≫ ・母乳が出る条件について:母親の意識と子どもがちゃんと吸えるかどうか ・母乳育児をしていく上での母親への情報提供(どこに相談していいのかわからない母親が多い) ・小児科医の役割、産婦人科医の役割、助産師の役割、そしてそれぞれの連携 ・母乳外来をどのように行っているか ・帝王切開後のカンガルーケアはどうしたらできるか ・入院中や受診時の医師の発言、また、意思と助産師の発言が違う場合の母親への影響 ・医師と助産師の歩調を合わせる難しさ ・小さい児・体重の伸びがあまり芳しくない児へのミルクを足すかの判断の具体例 ・参院の退院後の母親の不安や心配、アクシデントに対して、産院から地域から小児科から母親仲間から、どういったフォローがしていけるのか ・バースプランで、母児同室は何日目から希望しますか?と問うことに疑問を感じる ・スタッフ自身の母乳に対する正しい認識が少ない ・帝王切開後の母児同室について:帝王切開は、夫もOPに立会い、その後そのまま同室する。同室してみれば、出来るということがわかる ・母乳育児は『教育すること』よりも、『環境を整えること』が先(これはスタッフについても言える事なんだ?!)。とにかく、母児同室・頻回授乳・人口乳を与えない・・・この3つを始めること。 ・育児サークルを続けることの難しさについて ・高知で母乳育児が常識となるには
|

|
|||||||||||||